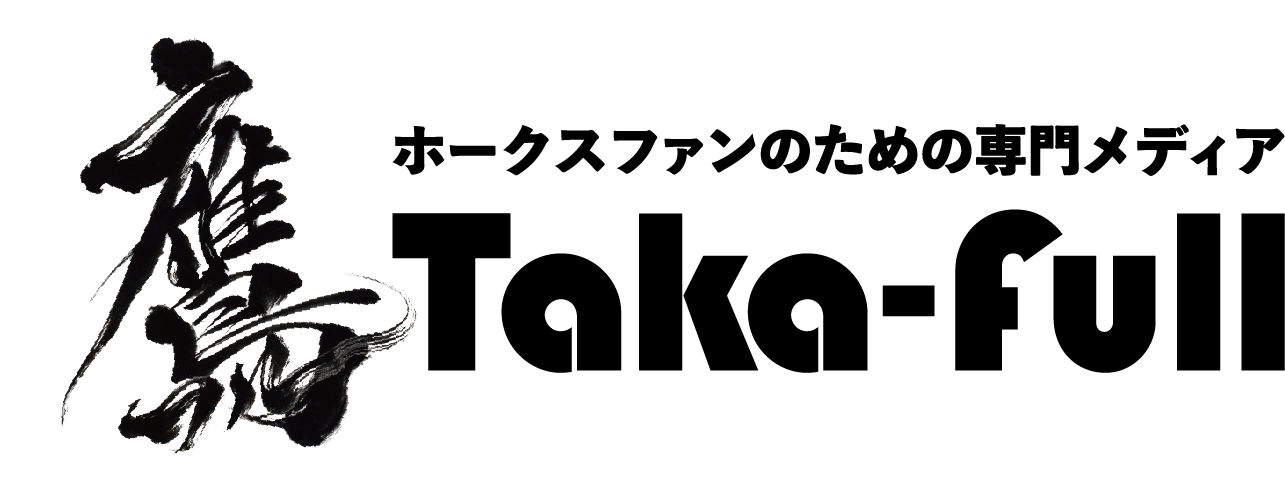選手が一喜一憂「ああ?!」
「HAWKSベースボールパーク筑後」の室内練習場で、若鷹たちが一喜一憂している。「ああ〜!」。悔しそうな表情で戻ってきたのは、育成3年目の重松凱人外野手。取り組んでいたのは、実在の投手の球を再現することのできる最新鋭の打撃マシンを用いた「アイピッチ検定」だ。
1人の持ち球は20球。その中で1〜16級のレベルに応じて課題が設定され、クリアすると次のステージへ行ける仕組みだ。一方で、6級を合格していない選手は動作解析を受けることができないという厳しい条件もある。重松は3月上旬、6級に挑戦したが「サードゴロのこねた打球を打ってしまって……」。引っ張りの打球速度が足りず、合格とはならなかった。
同検定は今季2年目を迎える。1軍レベルの選手よりも、若手や2軍で上を目指す選手にこそ自身の動作を理解すべきという話もあるが……。なぜ6級以上と設定するのか。そもそも、検定の目的は何なのか。城所収二データサイエンスコーディネーター補佐兼R&Dチーフ博士(スポーツ科学)に取り組みのゴールを聞いた。
室内練習場の打撃マシンが置かれている打席の横には打球速度などを表示するモニター画面が備え付けられている。持ち球20球のうち、平均速度や最高速度などで各級の合格基準が設定されている。挑戦は任意で、1度で合格すれば同日に次の級も受験することができる。
2024年にスタートしたこの検定。当初の目標は2軍で活躍していた選手が1軍に上がった時に好結果を残せない、その差を埋めることだった。城所氏は「多くの場合がストレート、速めの真っすぐに対して対応しきれていないことが原因」と分析する。
昨年のパ・リーグ投手の速球の平均球速は147.4キロ。対してウエスタン・リーグ投手の平均は143.3キロだった。「平均の球速も違うんですけど、3?4キロなんです。それ以上に速く感じるのは制球力の差が1軍と2軍では違うので。その制球力に対してたくさんチャンスボールが来るわけではないっていうのが実際のところ」と話す。「しっかりと1スイングで仕留められるというのをどうしたらいいのか」。その課題解決のために始まったのがこの検定だった。
昨季に最終級をクリアしたのは3人
目標は全てクリアした場合に1軍で活躍できるレベルに到達されること。そのために16段階のステップが設けられた。昨季は石塚綜一郎捕手、イヒネ・イツア内野手、中澤恒貴内野手の3人が最終級をクリア。しかし、石塚はシーズン途中に支配下登録をされ1軍デビューを飾ったもののOPS.624、イヒネは2軍で打率1割台と当初の目的が達成できたとは言い難かった。
「彼らが全て1軍の戦力になれているかと考えると、まだまだだなって。こちらとしては全てをクリアしたら1軍の戦力に足る技術を会得したという状態にしたかったので」。そのため、キャンプ前に改良を重ねると、1級から合格者が激減した。「ゲーム性を考えると、レベル1が難しすぎるとやる気がなくなってしまう。段階的にスキルアップして、それに応じた少し上のレベルの難易度が好ましいのかな」と再び調整を加えた。
では、なぜ6級以下は動作解析ができないのか。この日、重松は6級を合格できなかったため、動作解析は“お預け”となった。「6級以下はプロ野球じゃないということですよね。最低限レベル。結構厳しいです」と苦笑いしていた。育成選手だけでも約50人と巨大戦力を誇るため「全員を均等に計測することは難しく、優先順位をつけざるを得ない」と城所氏は現状を明かす。
すべて“平等”とはいかないプロの世界
プロ野球はレギュラーや定位置の奪い合い。それは、育成の“システム”を利用する優先順位にも同じことが言える。コーチや監督の判断のみだと、どうしても「なぜ受けさせてもらえないのか」という意見が出る。一方で6級は全て直球のみ。「プロ野球選手としては、ファストボールと分かっている球はしっかり弾き返せるようになるのが大前提。その上で、試合で対応していくためにどういう技術が必要なのか、体の使い方どうなっているのかを見れるように」と基準設定の意図を語る。
明確な基準が示されることで判断もしやすくなった。関川浩一コーディネーター(野手)も「もちろん、検定自体も改良を重ねているので全てをそれで判断するわけではないが、やっぱり一つの判断基準にはなりますよね。たくさん育成を抱える中で、コーチ陣も選手全員を同じ時間平等には見ることは難しい。明確な結果で判断するのは良いこと」と話す。
実際に選手にとってもモチベーションとなっている。すでに10級以上をクリアした大泉周也外野手は「色々な球種を打てるし、実際の投手に近い球速帯で練習できるので役立っています」と語り。一方で「目安があるのでいいことかなと思います」と付け加えた。重松も「育成はどうしても支配下の人よりはチャンスが少ないのものですけど、自分の可能性を広げるために1級も受かっていない人よりはチャンスがもらえる」と話す。一見厳しい目標設定も、育成選手の多いホークスならではの取り組みだといえる。
(川村虎大 / Kodai Kawamura)